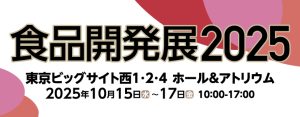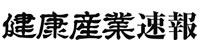(一社)Jミルクが28日に行った、第53回メディアミルクセミナーでは、タンパク質の“質”に関する話題が、立命館大学スポーツ健康科学部教授の藤田聡先生によって語られた。
「タンパク質の“質”と効果的な摂取法」
立命館大学スポーツ健康科学部教授 藤田聡氏
(以下、講演の要点まとめ)
■筋肉量の低下が様々なリスクに
加齢に伴い筋肉量が減少していくことで、転倒リスクが上がる。さらに骨格筋は代謝を担う組織でもあるため、筋量の低下が糖尿病発症のリスクを増加させる。中性脂肪やコレステロール値も筋肉量の少ない人ほど高い傾向にある。年齢にかかわらず、筋肉量の減少は、死亡リスクを増加させる。また、筋肉が減るとエネルギー消費も低下する。基礎代謝で消費されるエネルギーの22%を筋肉が占めており、筋肉の多い人の方が太りにくい。
■タンパク質は毎食摂取する必要がある
筋肉は、合成と分解を24時間続けている。食後にタンパク質の合成が優位になり、食事前には分解が優る。また、筋肉合成のスイッチを入れるのは必須アミノ酸だが、その中でも特に重要なのがロイシン。ロイシンが筋肉内のシグナル因子mTOR(エムトール)を刺激することで筋肉の合成スイッチが入ることが分かってきた。ただし、加齢に伴いロイシンに対する抵抗性が発生する。高齢になるほどより多くのロイシンが必要になる。
高齢者における3年間の追跡調査で食事からのタンパク質摂取量が多かった群では、少なかった群に比べて筋肉の減少を4割ほど抑制した。日本人の食事摂取基準では、タンパク質の推奨量が高まり、体重当たり1.06g/kg(おおよそ50~60g/日の摂取)。筋肉を維持する観点からみると、3食のタンパク質摂取量の合計で考えていては不十分で、タンパク質は貯められないので、1回の食事ごとにタンパク質を摂取する必要がある。その目安は20g程度だが、特に朝食でタンパク質を摂れていない人が多い。どの年代においてもその傾向にある。
■運動する際には質の良いたん白摂取を―ロイシンがポイント
有酸素運動に比べてレジスタンス運動(筋トレ)のほうが筋肉量増加には効果的。1回の筋トレの効果は、運動後から2日間維持する。年齢にかかわりなく長期的な筋トレをすることで筋肉を肥大化させることができる。筋トレによる筋肥大は、仕事量に依存するため、低強度の運動でも筋肥大は可能となる。
運動とタンパク質摂取を組み合わせることで、効果的に筋肉量の増加・維持ができる。タンパク質の「質」を考えると、筋肉合成のスイッチであるロイシンが重要となるが、とくに乳製品はロイシン含量が高いものが多い。高齢者の筋トレによる試験では、タンパク質摂取量と下肢筋量の関係性は有意傾向であったが、ロイシン摂取量と下肢筋量には正の相関関係が確認された。
筋トレの効果を最大に高めるタンパク質の量としては1.62g/kg体重/日と考えられ、高齢者では補食が必要となる。若年者では、夕食よりも朝食にタンパク質を足すことで、筋トレ効果が増大した。