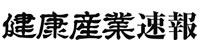健康食品GMPの重要性が増している。紅麹問題を受け、機能性表示食品制度の見直しで2年間の猶予期間のもとに健康食品GMPが義務化された。表示制度として製品を製造する届出者が全責任を負うため、今後は受託製造だけでなく、原料から販売までのサプライチェーン全体で安全性と品質確保で連携することが重要になってくる。国内で健康食品GMPの認証を手掛ける日本健康・栄養食品協会(日健栄協)と日本健康食品規格協会(JIHFS)の2団体では、原材料GMPを強化しており、1月には受託企業に特化した業界団体も誕生。一方、海外展開においては、サプリメントを法律で定義する諸外国からの要求事項として健康食品GMPは必須となっており、2団体への問い合わせも増えている。こうした中、米国におけるcGMP見直しの動きも出ている。
日健栄協・JIHFSともに原材料GMP強化
GMP(Good Manufacturing Practice:「適正製造規範」)は、原料の入庫から製造、出荷にいたる全工程において、製品の品質と安全性を保つよう定められた規則。健康食品GMPは、2005年の厚労省通知(H17通知)により、日健栄協とJIHFSの2団体により認定事業が開始され、20年間に亘る健康食品GMP取得企業数は、日健栄協153社182工場、JIHFS38社42工場の計191社224工場(2 月25日現在)。医薬品GMPのように、製薬メーカーに義務化され、製品ごとの許認可が要件である点と異なり、認証を目指す事業者の自主性に委ねられており、認証取得事業者は、受託・取扱製品それぞれの安全性と品質確保を維持するため、煩雑かつ膨大な作業を行っている(24〜25面トピックス参照)。
続きは、本紙3月5日発行号(1807号)に掲載。定期購読のお申し込みはこちらから
該当記事および過去のバックナンバーは、電子版ページからも閲覧いただけます。
■「受託製造企業ガイドブック2022年版」 好評販売中■
2017年版を全面改定し、「機能性表示食品への対応」を追加。各社の概要、特色、業況、連絡先がこの一冊に。健康食品・化粧品の製造、各種試験・分析依頼、原料調達などに、ぜひ本書をご活用ください